ママLabo(幼児・小学生を持つ母のグループ)
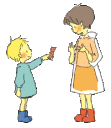
幼児 小学生を持つ母のグループは、日ごろの子どもとの
出来事や、こんなこと困ってる?どうすれば?ということを皆で話し合い共有する場です。
乳幼児Gから卒業すると、同じ年代の子どもを持つお母さんとの関わりは少なくなりますが、子どもたちは集団生活に入り、子育ての心配は尽きません。幼児・小学生を持つ母のグループでは読書を通してみんなで考えたり話したりしながら大切なことを見つけていきます。リーダーもお母さんの中から決めて、読書やテーマなども決めて話し合ったり、実習なども取り入れています。
若いお母さんを中心に、乳幼児を持つ母のグループと同じように絆が深められることを願っています。
2021年6月24日(木)(オンラインにて)
出席者 8名
読書 「よいことは必ず出来る」(『教育三十年』)

6月24日(木)に、今年度はじめてのママLaboを開催しました。8名の参加があり近況報告や読書をし、夏休みに取り組みたいことについても話し合いました。
お子さんたちの近況を聞くと、小学生のお子さんたちは、生活リズムの変化に対応する過程である様子。幼稚園生のお子さんは、新入園児のお世話を楽しんでいるという成長の姿。また、今年度幼稚園に入園したお子さんたちも、スムーズに園生活をスタートできているという報告がありました。
お母さんがたも、新年度のスタートで仕事や新しい役割などに忙しい毎日だったようですが、お子さんの小さな変化や成長を見逃さず、よく見ていることがみなさんの言葉から伝わってきました。
読書では、『教育三十年』から「よいことは必ず出来る」の箇所を読み合いました。先輩会員の参加もあり、子育て期とは違った視点の感想を聞くことができました。目の前のことばかりになってしまいがちですが、子育て真っ最中の「いま」から少し先へ視野を広げることができました。
最後は夏休みに子供達と取り組みたいことについて話し合い、昨年に続きオンラインでのラジオ体操と、「夏らしいものを発見したら投稿!」の2つになりました。もうすぐ始まる長い夏休み。楽しく過ごす助けになればと思っています。(T記)